Scrum Guide Expansion Packの動画を見たり、勉強会に参加して理解する

monotalk
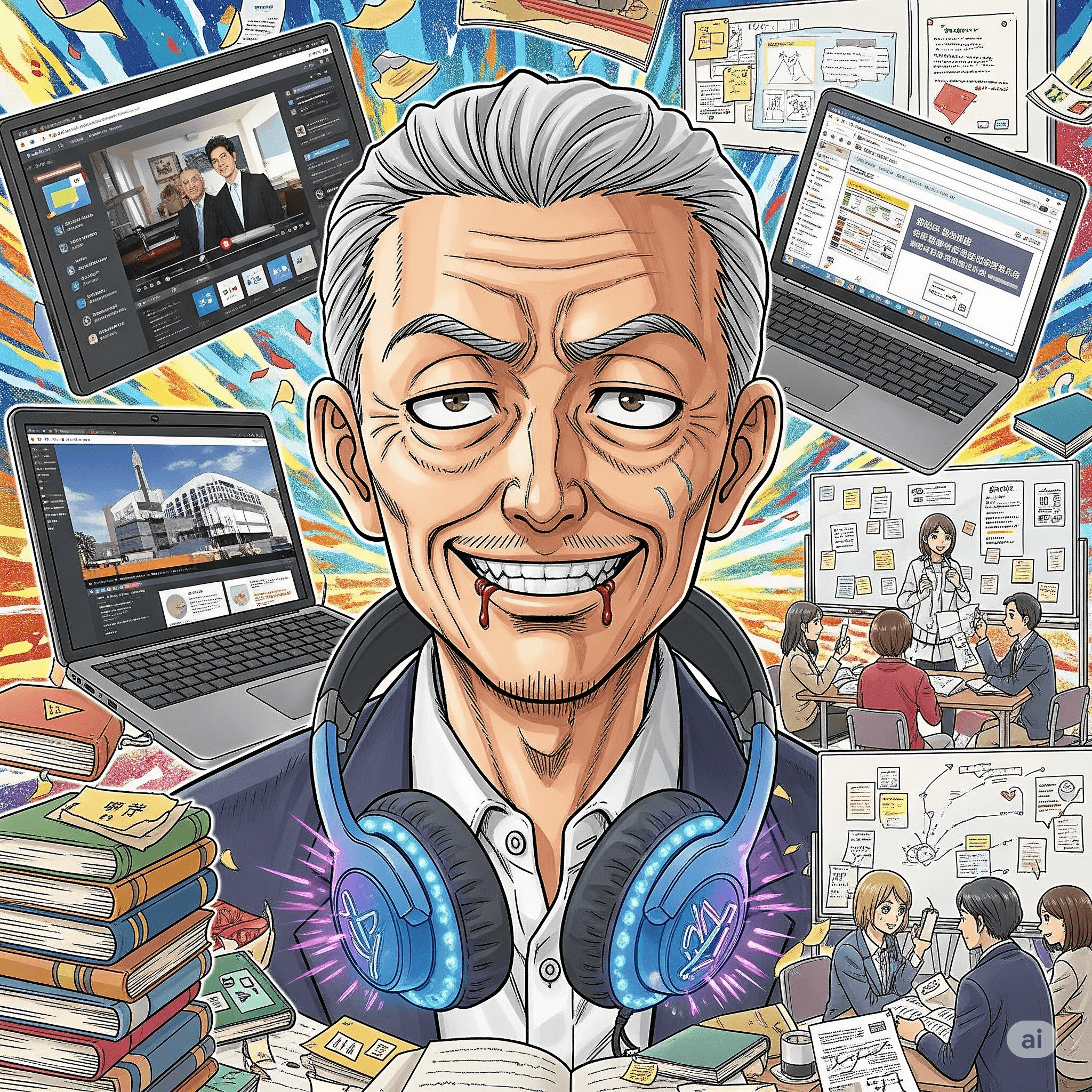
はじめに
2025年6月にScrum Guide Expansion Pack(SGEP)が公開されました。 Xでフォローしている人たちの発信で公開を知り、NotebookLMに登録して読んでいましたが、英語が得意ではないため、内容が十分に理解できませんでした。 2025年7月初旬にちょうど良く開催されたYouTube Liveや勉強会が開催されたので、見たり聞いて、メモを取り、その要約と個人的な感想をまとめました。
見た動画、参加した勉強会
-
(4) 緊急生配信「Scrum Guide Expansion pack大解剖」 - YouTube
2025年7月2日に配信されたNewbeeで、平鍋さんと、天野さんが議論した動画です。 -
【増枠】Scrum Guide Expansion Packについて話そう - connpass
2025年7月3日に実施されたオンライン勉強会です。
緊急生配信「Scrum Guide Expansion pack大解剖」
以下、生成AIに要約してもらったメモです。
## 緊急生配信「Scrum Guide Expansion pack大解剖」の要約
### 全体的な特徴
- **外向きアプローチの強化**: スクラムチームの外側への影響を重視
- **プロダクト開発組織への対応**: 会社の成長に伴う組織的課題への回答
- **豊富なリファレンス**: 149項目の詳細な参考情報を提供
- **ルールとプレイブックの統合**: 理論と実践の両方を網羅
### 重要な拡張ポイント
#### 1. ディスカバリーとデリバリー
- スクラムチームの責任範囲をディスカバリーまで拡張
- Feature Factory化への警鐘
- 受託開発文脈での課題への言及
#### 2. Outcome Done概念
- 従来のDefinition of Doneを成果レベルまで拡張
- ビジネス成果までの測定可能性を求める
- 組織によっては実現に時間がかかる可能性
#### 3. ロールとステークホルダーの明確化
- Product Developerへの名称変更
- ステークホルダーとサポーターの重要性強調
- プロダクトオーナーとプロダクトマネージャーの役割整理
### AI時代への対応
- **AIをチームメンバーとして位置づけ**: 保守的かつ現実的なアプローチ
- **人間の情熱の重要性**: AIにはできない「熱く語る」価値の強調
- **スクラムマスターの新たな役割**: AIとの向き合い方のサポート
- **Whyへの集中**: AIが作業を担当し、人間は本質的な部分に注力
### 実践への示唆
- **文脈に応じた解釈**: 画一的適用ではなく、組織特性に応じた活用
- **段階的導入**: 全てを一度に実装しようとしない
- **言葉づくりの重要性**: 「いいチームは言葉を持っている」
- **スケーリング対応**: 複数チーム環境での適用方法
### 課題と注意点
- 習熟していないチームには理解が困難
- 受託開発での適用の難しさ
- ステークホルダーとの関係性構築の重要性
- 既存のアジャイル実践との区別の必要性
Scrum Guide Expansion Packについて話そう
以下、生成AIに要約してもらったメモです。
## 「【増枠】Scrum Guide Expansion Packについて話そう」勉強会要約
### 基本情報
- **開催形式**: オンライン勉強会(21:00-23:00)
- **参加者**: スクラム実践者・関心のある開発者
- **目的**: Scrum Guide Expansion Pack(SGEP)の概要理解と議論
### Scrum Guide Expansion Packの特徴
#### 基本構造
- **位置づけ**: Scrum Guide 2020の拡張版
- **対象**: 実践者とステークホルダー両方
- **範囲**: ソフトウェア開発に限定されない製品開発全般
- **構成**: Why・Whatの拡張に焦点、149項目の豊富な参考情報
#### 理論的基盤の強化
- **複雑適応系**: ツリー構造でない組織の重要性
- **経験主義**: 観測可能なエビデンスに基づく意思決定
- **OODA概念**: 5つの価値とOODAループの関連性
- **システム思考**: 因果ループ図による適応型組織への進化
### 重要な拡張概念
#### 1. プロフェッショナリズム
- 技術的卓越性の追求
- TDD・アーキテクチャを含む継続的な技術向上
- 「常にやること・やらないこと」の明確化
#### 2. Discovery概念
- デリバリーだけでなくディスカバリーもスプリント内で実施
- 顧客期待の理解と価値発見プロセス
- Feature Factory化の防止
#### 3. Outcome Done
- 従来のDefinition of Doneを成果レベルまで拡張
- KPI的な定量・定性指標の設定
- プロダクトゴールへの積み重ね
#### 4. ロール・ステークホルダーの明確化
- **Product Developer**: 開発チームの新しい呼称
- **ステークホルダー**: 意思決定権を持つ関係者
- **サポーター**: チームを支援する役割
- **AI**: 開発チームメンバーとしての位置づけ
### 参加者の議論・見解
#### 肯定的評価
- **Getting Started**: スクラム導入の実践的ガイドとして機能
- **レイトマジョリティ対応**: スクラムに情熱を注げない人への説明資料
- **トレーナー支援**: スクラムを教える人向けのリファレンス
- **ステークホルダー対応**: 決裁権者との仕事に必要な概念整理
#### 課題・懸念点
- **説明不足**: 説明しないといけないことは盛り込まれているが、説明になっていない
- **複雑性**: 情報が多すぎて逆に理解が困難になる可能性
- **実装の難しさ**: Outcome Doneなど概念の現場実装の困難さ
- **文脈依存**: 組織の成熟度によって理解・適用レベルが大きく異なる
### 実践への示唆
#### 導入アプローチ
- **段階的適用**: 全てを一度に実装しようとしない
- **組織特性考慮**: 文脈に応じた解釈と活用
- **継続的改善**: 月次での定性・定量評価とリファクタリング
#### 成功要因
- **リーダーシップ**: 職位に依存しない動機付け能力
- **透明性・検査・適応**: 3本柱の徹底した実践
- **価値観の共有**: チーム内でのスクラム価値の浸透
個人の感想
見て、聞いて理解した感想を「👍(プラス)」「👎(デルタ)」形式で記載します。
- 「👍+」概要を理解したいという目的は達成された。
- 「👍+」実際に現場で起こったりする悩みポイントには刺さっているところがあり、解決へのヒントがあると感じた。
- 「👍+」
Scrum Guide Expansion Packについて話そうでプロフェッショナルプロダクトオーナーという書籍が言及されていて、読んでみたいと思えた。 - 「👍+」AI活用については、2025年の前半でとても進化したので、対象節を読んで理解を深めたいと感じた。
- 「👍+」参考文献がたくさんあり、積読本が生まれそう。
- 「👍+」手元でScrum Guide Expansion Packを登録したNotebookLMで検索しながら、聞いてたが理解が深まった気がする。
- 「👎▼」テキスト情報として十分にインプットできていないため、スクラムガイドとの違いだけが記憶に残っている。
- 「👎▼」Outcome Doneは対象となるプロダクト、組織の状況によっては、決めるのに長い時間がかかりそう。
- 「👎▼」日本語訳出てからじゃないと、「みんなで読んでみる」は厳しそう。
個人的には文書を読んでいない状態では違和感があるため、原文や日本語訳を時間をとって読んでみよう思います。すでに読んで理解されている方のざっくり説明をたくさん聞けたので、その効果もあり捗りそうです。
参考資料
関連記事
GitHub Actions issue-metricsの記録をもとにAIにふりかえりをしてもらう
GitHub ActionsAIGitHub Copilot
続きを読む →類似度: 15%
actions/ai-inferenceを使ったGitHub ActionsによるAIコードレビュー自動化
GitHub ActionsコードレビューAI
続きを読む →類似度: 14%
NotebookLMを使って少人数デイリースクラムのふりかえりをしてみる
デイリースクラムふりかえりNotebookLM
続きを読む →類似度: 14%
Next.jsのBlog Starter Kitが初心者の学習に良いと思う
Next.jsブログ学習
続きを読む →類似度: 13%
10年近く勤めたB2BのSaaSプロダクト事業会社を退職します
キャリアSaaS転職
続きを読む →類似度: 12%