退職に伴う社内アジャイルコミュニティの引き継ぎで起きたこと、今後のコミュニティ活動について

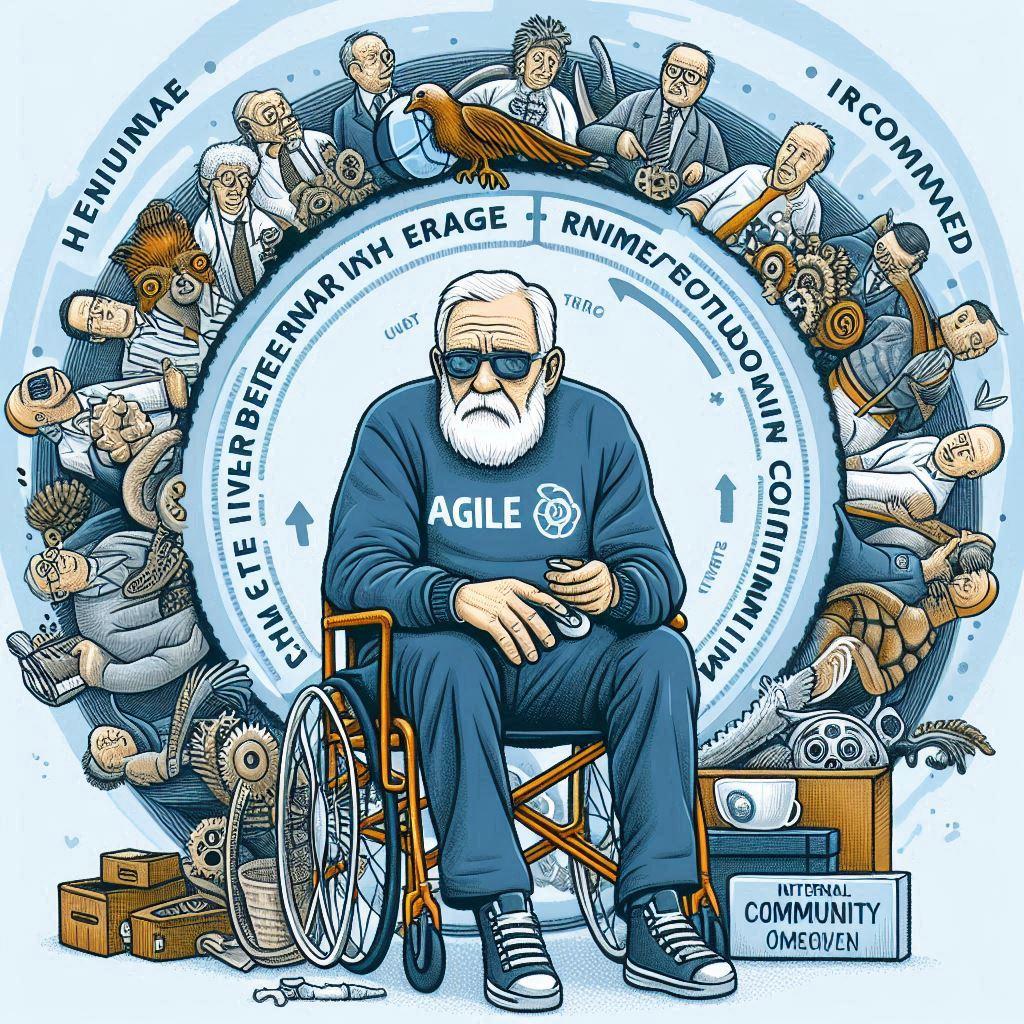
はじめに
会社を退職する際、自分が立ち上げたアジャイルコミュニティの引き継ぎを経験しました。 この記事では、コミュニティの運営内容、退職時に引き継いだ作業内容、そして引き継ぎ後に起きた変化について共有します。
コミュニティ活動の内容
前職のB2B SaaS事業会社では会社の「部活動」制度を活用して社内アジャイルコミュニティを運営していました。
メンバー1名あたり月1000円の予算が配分され、年間1万2千円が支給されるため、このお金を活動費用にあてていました。
メンバー数は、非アクティブなメンバーを含めて20名程度で、定期的に参加するアクティブなメンバーは10名程度でした。
設立の動機
動機に関しては、以前記事にまとめているので、興味ある方がいたらこちらをご確認ください。
参考にした情報(2023年9月当時を思い出す)
コミュニティ立ち上げ時は、以下の情報を参考にしました。
マネーフォワードの社内コミュニティの紹介セッション
- (457) 転職したので社内にアジャイルコミュニティを作ったら、思いの外楽しくなってきた〜!! - YouTube
- 転職したので社内にアジャイルコミュニティを作ったら、 思いの外楽しくなってきた〜!! - Speaker Deck このスライドを見て、リーンコーヒーが良さそうと思いコミュニティのメインの活動内容としました。
レッドジャーニーの社内コミュニティに関する記事
- 社内にアジャイルコミュニティを立ち上げよう|市谷 聡啓 (papanda)
市谷さんが投稿している上記の記事も参考にしていました。
直接声をかけることは効果があったという記憶があります。
主な活動内容
私の退職間際は以下のような形に落ち着いていました。
定期的な活動
-
月2回のリーンコーヒー
メンバーが持ち寄ったトピックについて自由に議論していました。 -
月1回の読書会
書籍は部費で購入してアジャイル関連書籍の輪読会を行っていました。 -
隔月の専門家とのセッション
天野 祐介 (ama_ch)|note さんに相談して、noteのメンバーシップの法人契約プランを作ってもらい、隔月でメンバーシップの記事についての質問と、仕事での悩みを共有する機会を設けてもらいました。
不定期な活動
主に新しい部員の入部を期待、社内向けの宣伝目的、単純な興味半分で以下のような活動を行う予定でした。
退職することになったので、窓口を繋ぐところまでは実施、「後のことは任せた!」という状態になってしまいました。。
-
システムコーチング体験
システムコーチの方にお願いして、コミュニティのシステムコーチングを実施頂きました。
有休消化期間を挟んで、全セッションに参加できなかったのが、心残りではあります。 -
スクラム研究への協力
スクラムの研究者の方の調査に協力して、アンケートやインタビューなどを実施する予定でした。
現在(2025年4月)まさに進んでる頃なのではと思われます。
コミュニティの成長段階
2023年9月に立ち上げたコミュニティは、2025年2月までで以下のような変遷をたどりました。
-
形成期(最初の6か月)
キックオフMTGの実施し、初回は20名近く集まっていた気がします。
当初はリーンコーヒーとOSTの両方を実施する計画でしたが、両者の差別化ができなかったため、OSTは中止しました。 -
確立期(6か月〜1年)
活動内容が定着し、安定した運営状況にあったと言えます。一方で、新しい試みや変化は少ない状態でした。 定期の活動はこの辺りで固まっていきました。参加者は4〜10名程度で固定化した状態でした。 -
混乱期(1年目〜)
不定期の活動と絡めて、新しい部員を募集して新しい人が入ってきたり、私自身が退職することになり、代表の引き継ぎをして混乱が生じていた気がします。
退職時のコミュニティの作業で引き継いだこと
2025年1月にコミュニティメンバーに退職する旨を伝えたあと、以下の作業を引き継ぎました。
とくに個人的に作業を抱えているという認識はありませんでしたが、コミュニティの作業は通常業務と並行で実施してもらうことになるため、若干申し訳なく感じました。
契約・管理業務
-
NDA(秘密保持契約)の管理方法
外部の方と関わる際に、コミュニティ活動とはいえ会社の情報を扱う場合があるので、NDAの締結をして頂いていました。その手順の説明と、過去のNDA契約書の共有を行いました。 -
外部支援者との発注契約の手続き
こちらも契約書関連です。外部支援者の方と発注契約を結ぶ必要があり、そのあたりの手順の説明と、契約書の共有を行いました。 -
請求処理の進め方
発注契約の後の、請求処理の進め方、請求時期についての引き継ぎを行いました。
運営実務
-
年間予算計画の作成
部活動の予算をどう使うか記載した年間予算計画を会社のコーポレート部門に提出する必要がありました。そのため、その作成方法についての説明を行いました。 -
経費精算の手順
部活動の予算で購入した書籍の経費精算方法の説明を行いました。 -
カレンダー管理とスケジューリング
Googleカレンダーに登録していた定期のミーティングと、不定期のミーティングの管理者の変更を行いました。
引き継ぎ後に感じられた変化
引き継ぎを終えて2025年2月から有休消化期間に入りました。その後、以下の変化が起きているように感じています。なお、これはあくまで私の視点であり、当事者の方は異なる見解を持っているかもしれませんが、記録のために残しておきます。
新しい代表者のモチベーションの変化
コミュニティ代表を引き継いだメンバーは、責任感からか、これまで一度も足を運んだことのなかった外部コミュニティに参加し始めました。参加してみると楽しさを感じたようで、その体験を周囲に積極的に共有していました。
この活動の結果、他のメンバーにも「自分もコミュニティに参加してみよう」という気持ちが広がっていきました。特に、元々興味が薄かった人が自ら興味を持ち始めたことが重要な要因だと感じています。
コミュニティのアクティブユーザー数の増加
これは現在も続いているのかは不明ですが、退職のタイミングでの参加者の増加が観測されました。
退職セレモニーとしての参加という意味もあるかもしれません。また、コミュニティが若干不安定な状態になったことや、私という古参メンバーの離脱で新規メンバーが入りやすくなった可能性もありました。
システムコーチングの体験から感じたこと
退職直前〜有給期間消化中に実施したシステムコーチングセッションは、気持ちや感情の引き継ぎに効果的でした。退職時期を狙ってコーチングをお願いしたわけではなく、たまたま時期が重なったのですが、結果として良い影響をもたらしました。このセッションはコミュニティの方向性を決める目的で実施していただきました。
システムコーチングから得た気づきは以下の通りです。
- コミュニティに集まるメンバーの目的は、メンバーごとにそれぞれある。
- それが行動として表面化するケースもしないケースもあることに気づいた。
- 私個人はコミュニティに明確な目的を持っていたことに気がついた。
- 実態はもっとふわりとしたものであった。
- 私の発言の影響力が自分が思っていた以上に強いことがわかった。
- 場を不安定にする発言を意識的にも無意識的にもしている。
- 他者との感情、価値観の違いを感じることができた。
- 頭で考えると当然のことだが、それを体験を通して実感できた気持ちになる。
より多様性を受け入れ、参加者の自由な出入りを許容する場づくりができていれば良かったと感じています。また、リーンコーヒーや読書会の内容が難しすぎたのかもしれないと考えています。
コミュニティの成功要因について
課題はあったものの、1年以上継続して活動でき、メンバーの中に定着した参加者も生まれたことから、社内コミュニティの運営としては一定の成功を収めたと考えています。その背景には、以下のような要因があったと思われます。
-
ある程度の社歴があり、信頼貯金が貯まっていた
- 入社して8-9年目でコミュニティを立ち上げたため、ある程度信頼貯金が貯まっていました。「コミュニティを作ろうと思っているのですが、どうですか?」と声をかけただけで、それなりの人数が集まってくれました。
-
コミュニティ内に影響力のあるメンバー(部長クラス)が参加していた
- メンバーの中に部長クラスの方がいました。この方はワークフローなどの承認権限を持っていたため、手続き関連の承認を得るハードルが低いというメリットがありました。
-
トップダウンのプレッシャーがあった
- ちょうど、会社としてトップダウンでアジャイル開発|スクラムを推進する時期と重なり、メンバー層にはキャッチアップのプレッシャーが若干かかるタイミングではあったと思います。
退職が成長機会になるという気づき
私の退職は、残されたメンバーにとって成長の機会になったと感じています。在職中にもっと意図的にこのような機会を作れていれば、さらに良かったとは思いますが、退職というイベントがきっかけでその変化を観測できたことは、不完全ながらも一定の成果として満足しています。
おわりに
現職でのコミュニティ活動について、少しずつ考えはじめているのですが、立ち上げる時期はとても重要に感じていて、以下2点の様子を見ている状態です。
- 自分の信頼貯金の貯まり方
- 会社がそのコミュニティ活動を必要とするフェーズ
前職はアジャイルコミュニティでしたが、実は「コミュニティ活動をする」こと自体がアジャイルだと感じています。会社に集まる人が必要としていること、そして私自身が興味を持てることであれば、どんなコミュニティ活動も価値があるのではないかと考えています。